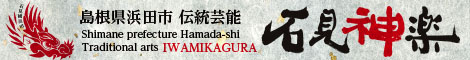儀式舞
帯 舞(おびまい)

■ 登場人物
舞人2人
■ 神楽歌
紫の雲の中より現はれて
八つ幡雄々しあれをこそ見よ
八つ幡雄々しあれをこそ見よ
■ あらすじ
衣食住の「衣」に感謝をする神楽で赤・白の帯を持って舞います。神功皇后が応神天皇をお産みになられたとき、神の御心を慰め解きほぐすため、天より降りてきた帯とされ、神の心を和らげるものです。


数年に一度ある大元祭などでしか見ることのできない特別な演目だよ。
帯の流れが美しく、ゆったりうっとりと見る舞だよ。
帯の流れが美しく、ゆったりうっとりと見る舞だよ。
鈴神楽 塩祓 真榊 帯舞 神迎 八幡 神祇太鼓 かっ鼓 切目 道がえし 四神 四剣 鹿島 天蓋 塵輪 八十神 天神 黒塚 鍾馗 日本武尊 岩戸 恵比須 大蛇 五穀種元 頼政 八衢 熊襲 五神