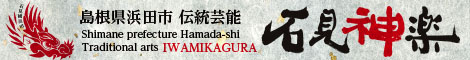能 舞
かっ鼓(かっこ)

■ 登場人物
神禰宜(かんねぎ)
■ あらすじ
この舞は、次の演目「切目」と一連の舞。切目の王子に仕える神禰宜(かんねぎ)が、高天原から熊野大社に降りた羯鼓と呼ばれる宝物の太鼓を祭礼神楽の為に適当な所へ据えようとします。なかなか神様の気に入る所に据えることができずに何度も据え替える様子をリズミカルな太鼓の調子にのり、滑稽なしぐさで舞うのが特徴の神楽です。


ユニークな顔の神禰宜が、太鼓を置く場所を悩む仕草がおもしろい。
最後によい場所に置いた時には、大喜びで太鼓を打ち鳴らすので、見ている方もとても晴れやかな気分になるんだ!
最後によい場所に置いた時には、大喜びで太鼓を打ち鳴らすので、見ている方もとても晴れやかな気分になるんだ!
■ 口 上
神禰宜「そもかやうに候ものは、紀伊の国熊野の権現、切目の王子に仕へまつる神禰宜にて候。時にこの太鼓、高天の原より降り来りし時、てんてんどうどうと打ちみたまへば、天下泰平、国家安穏と鳴りひびき、又方ひらを打ちみたまへば、五穀豊穣、商売繁昌、なほなほ(御當所)大繁昌と鳴りひびいて候。その後熊野の宮に納まり、御寶物の太鼓と相成り候。然るに當社御祭禮御神楽につき、この太鼓よろしき處に据えおき歸れよとの詔を受け、これまで進み出でて候。」
神禰宜「さて羯鼓据えおき候處、余り事むつかしき大御神にて、高ければ高いとおつしやる、低ければ低いとおつしやる、高き低きの真中處に今一度据えかへたく、尚々伶人たち御はやしなさるべく候。」
神禰宜「やうやう羯鼓据えおき候ほどに、切目の王子、この處に御出現ましまして、村中安全の御祈祷なされ候間、神姿をしづしづと御拝みなさるべく候。」
鈴神楽 塩祓 真榊 帯舞 神迎 八幡 神祇太鼓 かっ鼓 切目 道がえし 四神 四剣 鹿島 天蓋 塵輪 八十神 天神 黒塚 鍾馗 日本武尊 岩戸 恵比須 大蛇 五穀種元 頼政 八衢 熊襲 五神